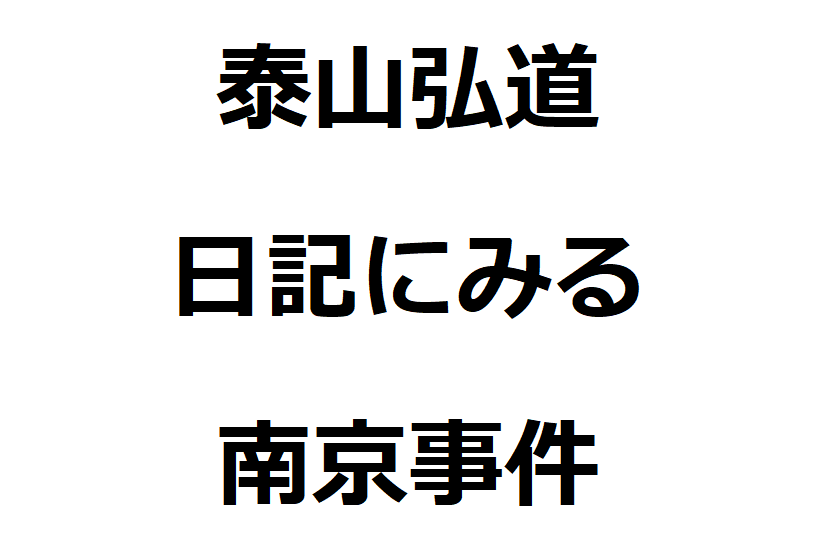泰山弘道は、海軍の軍医大佐として南京陥落後に現地に赴いた際につけていた日誌(日記)が公開されています。
この従軍日記によれば、泰山弘道海軍軍医大佐が南京に入ったのは南京陥落から3日が経過した昭和12年12月16日とされていますが、陥落から間もない南京市街の状況が記録されているため貴重な資料と言えます。
南京陥落後の市街の状況については南京攻略戦に参加した兵士が記した日記や手記が多数公開されていますが、それらが実際に南京攻略戦で直接戦闘に携わった将兵の記録である一方で、泰山弘道の従軍日記は直接的には戦闘に関わらなかった立場の人間による記録であるところに特徴があると言えるかもしれません。
では、泰山弘道の従軍日誌は南京で起こされた日本軍の暴虐行為についてどのように記録しているのか確認してみましょう。
泰山弘道の従軍日記は南京事件をどう記録したか
(1)昭和12年12月16日「ゴム袋の上に乗れるが如き緩かなる衝動」
泰山弘道従軍日記の昭和12年12月16日には、南京の下関(シャーカン)に到着した泰山が自動車で南京市街に入る際の情景を次のように描写しています。
〔中略〕徐に進む自動車は、空気を充満せるゴム袋の上に乗れるが如き緩かなる衝動を感ぜしめつつ軋るあり。之れ車が無数の敵屍体の埋れる上に乗れるなりと。さもあるべし、土の層の薄き所を進むに、忽ち土の中より肉片の泌み出づるあり。凄惨の状筆紙につくしがたし。
出典:海軍軍医大佐泰山弘道従軍日記 昭和12年12月16日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ422頁上段
漸く門を潜り抜けて南京側に出づれば、敵の屍体累々たるが黒焦となり、鉄兜も銃剣も黒く燻りて、鉄条網に用いたりし針金と絡まり、門柱の焼け落ちたる木片と相重なり、堆く積める土嚢も黒く焼けて、その混乱と酸鼻の景は譬へん方なし。
下関は南京城の北西に位置する把江門の外側に位置する地域のことですが、揚子江対岸の浦口への唯一の脱出路だったことから日本軍の包囲殲滅戦で逃げ道を塞がれ統制を失った中国軍守備隊と避難民の多くが、対岸に渡河して日本軍から逃れようと12日の夜頃からこの下関に殺到しました。
こうして下関に集中した敗残兵や市民の一部には、逃走を制止しようとする中国軍の部隊と衝突して死傷者を出すような事例もありましたが(※蔣公榖『陥京三月記』※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ 630頁、程奎朗『南京城複廊陣地の構築と守城戦闘』南京戦史資料集Ⅱ 494頁)、そのほとんどすべては追撃する日本軍に掃蕩されたり、河に漕ぎだした筏の上で長江(揚子江)に停泊していた日本海軍艦艇に銃撃されるなどして殺されています。
また、南京陥落後に行われた城内掃蕩で捕らえられた敗残兵捕虜の多くが下関や長江(揚子江)河岸に連行されて処刑されたことも、日本軍兵士の日記や手記、証言などから明らかにされていますから、そうして日本軍に殺された中国人敗残兵と市民の多くが、この道路の下に埋められていたため「充満せるゴム袋の上に乗れるが如き緩かなる衝動を感ぜしめ」るような状態になっていたのでしょう。
この点、この記述については虐殺を否定する人たちから「当時の車体の低い車でそんなデコボコの道を通れるはずがないではないか」などという意見も聞かれますが、これに似たような描写は、たとえば昭和13年(1938年)1月に南京を視察に訪れた矢次一夫の回想記や映画『南京』の録音技師だった藤井慎一氏の証言、その他当時南京にいた外国人の記録など数多く存在しますし、下関ではありませんが西門外の事例として南京攻略戦に参加した牧師の井之脇定二氏の証言など、似たような証言は山ほどあります。
屍臭といえば、これの一番ひどかったのは、下関を通過したときであった。私が、ハンカチを出して鼻を押えたのを見て、中原大佐〔南京駐在海軍武官〕が、この辺が一番戦さの激しかったところだと言い、いま通っている道路の下には、何万と知れぬ中国兵の屍体が埋められている、とも言い、この辺で戦死した中国人は、十数万と伝えられているほどだと言う。〔中略〕だから、この地下には、おそらく七、八万以上の屍体が埋められていると考えられるが、いくら穴を掘っても掘り切れるものではないので、自動車が通るとき、ふわ、ふわっとしていたのはそのせいですよ、という(矢次一夫『昭和動乱私史』上)。
出典:矢次一夫『昭和動乱私史』上 ※吉田裕『天皇の軍隊と南京事件』青木書店112∼113頁より孫引き
挹江門附近は物凄い死体で、死骸の上に板を渡し、その上を自動車が通っているほどだった。
出典:鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』文春文庫 241頁※藤井慎一氏(映画『南京』の録音技師)の証言
日本軍の下関門占領によって守備隊の大虐殺が起きた。中国兵の死体は砂嚢の間に山積みにされ、高さ六フィートの塚をなしていた。十五日の夜がふけても日本軍は死体を片づけず、しかも、二日間にわたり軍用車の移動がはげしく、死体や、犬・軍馬の死がいの上をふみつぶしながら進んでいった。
出典:洞富雄編『日中戦争南京大残虐事件資料集 Ⅱ』青木書店 283頁※ダーティン記者の証言(「下関門」はおそらく挹江門のこと)、※洞富雄『決定版【南京大虐殺】』徳間書店 278頁上段
「江岸に通ずる下関門のところでは、人間や馬の死体が恐ろしくも四フィートの堆積をなし、それらの上を二輪荷馬車(car)や貨物自動車(lorry)が通って、門を出入りしているのだった」
出典:『タイムズ』1937年12月17日上海発、18日号掲載※洞富雄『決定版【南京大虐殺】』徳間書店 277頁下段※マクドナルド記者のレポート
城門のありさまについてはすでに述べたとおりです。われわれは文字通り死人の山をこえて車を走らせてゆかねばなりませんでした。その光景はことばでは言いあらわせません。私はこの車で出かけたときのことをけっして忘れないでしょう。
出典:洞富雄編『日中戦争南京大残虐事件資料集 Ⅱ』青木書店 32頁※洞富雄『決定版【南京大虐殺】』徳間書店 277∼278頁※マギー牧師の証言
一九七七年八月二十二日午後八時のNHK放送『映像の証言』に出られた南京攻略戦参加の牧師井之脇定二氏は、西門外には幅三十メートルばかりの戦車壕が掘られていて、これが死体で埋めつくされており、その上を馬に輜重車をひかせて渡ったことを、語っていた。
出典:洞富雄『決定版【南京大虐殺】』徳間書店 278頁上段
したがって、この泰山弘道従軍日記に記述された「充満せるゴム袋の上に乗れるが如き緩かなる衝動を感ぜしめ」るような道路が、実際に当時の下関周辺に存在したことは否定できない事実と言えるでしょう。
ところで、先ほど述べたように南京攻略戦は包囲殲滅戦で下関に殺到した民間人だけでなく、敗残兵の多くも南京市街の路上に銃器や軍服を投げ捨てていている状態で、一部の敗残兵に散発的な抵抗があったとしても司令官の唐生智ら軍幹部は既に揚子江を渡って逃走しているような状態です。
中国軍の指揮系統は崩壊していて組織的な抵抗はできない状況だったのですから、ほとんどの敗残兵は戦闘意識を喪失した無害な敗残兵にすぎなかったわけです。
そうであれば、敗残兵に対しては降伏を勧告して投降を促し武装解除して捕虜として人道的な配慮を取るべきでしたし、それはハーグ陸戦法規の要請するところでもありましたから、仮に下関に捨てられた死体が戦闘によるものであったとしても、その戦闘に法的な正当性(違法性阻却事由)は存在しませんので、日本軍の敗残兵掃討は違法なものであったというほかありません。
また、仮にその下関に捨てられた死体が捕虜の処刑であったとすれば、国際法規上は捕虜の処刑に際して軍事裁判(軍法会議)にかけて罪状を認定することが求められており、軍事裁判(軍法会議)を省略した処刑は認められていませんから、軍事裁判(軍法会議)を経ることなく即座に実行された捕虜の処刑は国際法違反となります。
したがって、この泰山弘道従軍日記に記述されている道路下に埋められていた無数の「屍体」については、仮に戦闘によるものであったとしても捕虜の処刑によるものであったとしても、いずれにしてもその殺害は国際法に違反する「不法殺害」ということになりますので、下関を守る中国軍が逃走する中国兵を制止するために殺害した一部の死体を除いて、日本軍による「虐殺」によるものと認定しなければならないでしょう。
(2)昭和12年12月16日「木綿棉襖の便衣は、恰も繿縷の如く道路を埋め」
泰山弘道従軍日記の(1)に続く箇所では、下関から市街に続く道路に散乱する中国軍兵士の死体を次のように描写しています。
市内に近づくに従い、敵の遺棄せる藍色木綿棉襖の便衣は、恰も繿縷の如く道路を埋め、処々にカーキー軍服いかめしく革の脚絆を穿ち、手足の関節強直して仰臥せる敵将校の屍骸をも見るあり。
出典:海軍軍医大佐泰山弘道従軍日記 昭和12年12月16日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ422頁上段
この部分の記述からは、総崩れとなって統制を失った敗残兵が軍服を脱ぎ捨てて下関方面に逃走していたことがわかります。
この部分には銃器類の描写が見られないので、市民の平服に着替えて便衣した兵が銃器をもって下関方面に逃走した可能性もありますが、便衣して日本軍に抵抗するなら下関ではなく逆方向の市街の方で便衣を脱ぎ捨てて市内に潜伏するはずですし、南京陥落後に散発的な抵抗はあっても組織的な抵抗が起きていないことを考えれば、ここで軍服を脱ぎ捨てた敗残兵はここに至る前に銃器類を投げ捨てたか、銃器を所持していても戦闘意識を既に失ってここまで逃げて来たと考えるのが自然でしょう。
そうであれば、下関に捨てられていた死体のほとんどは、戦闘意識を喪失した無害な敗残兵だったということになりますので、この記述からは、下関に捨てられていた死体のほとんどが、敗走を留めるために下関の中国軍部隊に射殺された一部の死体を除いて、戦闘意識を喪失した無害な敗残兵が日本軍の敗残兵掃討によって処刑されたものであったことが想像できることになります。
(3)昭和12年12月16日「幾千の敵兵が魂消えゆく音なり」
泰山弘道従軍日記の昭和12年12月16日には、(1)で引用した道路を経て南京市内に入った泰山大佐が、夜に入って聞こえてきた敗残兵掃討によるものと思われる無数の銃声について次のように描写しています。
時々静寂を破る機銃の音は、抗日の執念抜くべからざる幾千の敵兵が魂消えゆく音なり。凄絶愴絶の光景之れ新戦場の夜半なり。
出典:海軍軍医大佐泰山弘道従軍日記 昭和12年12月16日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ422頁下段
この記述からは、南京陥落から3日が経った16日においても、市内で敗残兵掃討が行われていたことがわかります。
この点、この時期にも敗残兵による散発的な抵抗はあったと他の日記や手記などに記録されていますので、聞こえてきた銃声が市内に取り残された敗残兵との戦闘によるものか、それとも捕虜を処刑する際のものか、それは判然としません。
仮にその銃声が敗残兵との戦闘によるものであったとすれば、それによって殺害される中国兵については国際法規に照らしても問題がないように思えますが、先ほども説明したように、南京攻略戦は包囲殲滅戦で四方を日本軍に取り囲まれた中国兵は統制を失って既に総崩れとなっていた状態ですから、散発的な抵抗があったとしても、もはや帰趨は決していて敗残兵による南京奪還は不可能な状態となっています。
そうであれば、ハーグ陸戦法規は陸戦によって交戦する戦闘員に対して人道的な配慮を取ることを要請しているのですから、散発的な抵抗を続ける敗残兵に対しても降伏を促して投降を勧告し武装解除して捕虜として人道的な保護をすべきだったはずです。
また、敗残兵の掃討に関しても、市街に取り残されたほとんどの敗残兵は銃器を投げ捨て軍服を脱ぎ捨てて平服に着替えたうえで避難民にまぎれて潜伏しているわけですから、事実上もはや戦闘意識を喪失した無害な敗残兵に過ぎませんし、捕虜にしたのであれば軍事裁判(軍法会議)を経ることなく処刑することはできませんから、軍事裁判(軍法会議)を省略して即時に処刑することは国際法規に違反する「不法殺害」と言わざるを得ません(※この点の詳細も→南京事件における捕虜(敗残兵)の処刑が「虐殺」となる理由)。
したがって、この泰山弘道従軍日記に記述された16日夜に聞こえてきた銃声は、それが処刑のためのものだけでなく、仮に敗残兵を掃討するためのものであったとしても、日本軍の国際法規に違反する「不法殺害」によるものであって「虐殺」によるものであったということが言えます。
(4)昭和12年12月17日「彼は尚お紙片を拾い来りて…執拗に憐を乞う」
泰山弘道従軍日記の昭和12年12月17日には、助けを求めてすがってきた敗残兵を日本軍が処刑する場面が次のように生々しく具体的に記録されています。
揚子江の波打際に進めば、岸辺に築ける石垣の陰より、便衣を着けたる二人の敗残支那兵現われ、我等に向い手巾を振り何事をか合図するものの如し。〔中略〕彼等の一人は、我等を追い来りて、地に伏してチナチナと叫びながら救を乞う如きも、既に頭部には傷を負い、流れし血潮は顔面に凝着して、褐色の漆を塗りたるが如し。我等は今尚抗日思想抜くべからざる敵兵を処罰する場所えと急ぎつつあれば、彼に碼頭の方へ行き、関係者に救を乞うよう手真似にて示したるも、彼は尚お紙片を拾い来りて、木炭を以て何事か書き筆談せんとするものの如く、執拗に憐を乞う。折しも騎銃を肩にせる後備兵と見ゆる我陸軍の兵が帰り来れるを以て、彼の隊長に此の支那兵を引渡すべく告げて、余と加藤主計大佐は歩を進めながら後を顧るに、我兵は詮方なしとや思いけん、敵兵を後に向かしめたりと見るや、其場に銃口を支那兵の背部に当てて引金を引く。
出典:海軍軍医大佐泰山弘道従軍日記 昭和12年12月17日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ422頁下段∼423上段
「便衣を着けたる二人の敗残支那兵」としていますから、泰山弘道には軍服を脱ぎ捨てて市民の平服に着替えた敗残兵に見えたのでしょう。「手巾を振り何事をか合図する」とあるのはハンカチか布切れを振りながら合図してきということなので、その「便衣を着けたる二人の敗残支那兵」に敵対意思が全くなかったのがわかります。
「頭部には傷を負い、流れし血潮は顔面に凝着して」いたという部分からその敗残兵が大怪我をしていたことがわかりますし、「紙片を拾い」「何事か書き筆談せんと」して「執拗に憐を乞う」とあるので、もしかしたら仲間の誰かか民間人が頓死の重症を負っていて助けてほしいと縋りついてきたのかもしれません。
この記述からは、全く敵対行動をとっていない無害な敗残兵が日本軍に助けを求めてきたことがわかりますが、泰山軍医大佐からこの敗残兵二人を引き継いだ陸軍部隊が「其場に銃口を支那兵の背部に当てて引金を引く」ことによって射殺してしまっています。
これはもちろん、「虐殺」以外の何物でもありません。
布切れを振りながら合図してきたのなら武器を捨てて投降していることになりますが、ハーグ陸戦法規の「第23条ハ」は「兵器を捨て又は自衛の手段盡きて降を乞へる敵を殺傷すること」を明確に禁止していますので、この陸軍兵の行った処刑は国際法規に違反する「不法殺害」としか言えないからです(※この点の詳細も→南京事件における捕虜(敗残兵)の処刑が「虐殺」となる理由)。
この事例は、南京の敗残兵掃討に関わった日本軍が、敵対行動をとる敗残兵だけでなく戦闘意識を喪失して危険性のまったく無い従順な敗残兵を無慈悲に当たり前のように殺害していたことがよくわかる記録といえるでしょう。
南京事件において日本軍が行った捕虜の処刑については、敗残兵が敵対行動をとったからだなどと正当化する意見がありますが、そうした敵対行動をとらない敗残兵であっても、この事例のように無慈悲に処刑されていたのです。
(5)昭和12年12月17日「我が日本刀の切味を喫したる敵の死体六、七十あり」
泰山弘道従軍日記の昭和12年12月17日の夕方の部分には、日本刀で殺害されたものと思われる中国軍の死体を見つけた際の情景を次のように描写しています。
〔中略〕道を返して上流なる堤防の内側を窺うに、我が日本刀の切味を喫したる敵の死体六、七十あり。南京市街戦は如何に激しかりしかを思わしむ。
出典:海軍軍医大佐泰山弘道従軍日記 昭和12年12月17日※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ424頁下段
この点、日記は「市街戦は如何に激しかりしか」と記述していますので、この「60∼70」の死体は一見すると戦闘の中で殺害されたようにも読めます。
しかし、仮に戦闘中であったとすれば、60∼70名もの中国兵が銃や手りゅう弾で応戦している中に日本軍兵士が日本刀で突撃して斬り殺したことになりますが、日本兵が南京の城内に侵入した時点で南京は既に陥落状態にあって日本軍は圧倒的な兵力で敗残兵を掃討している状態なので、軍事的に圧倒的有利な立場にある日本兵が、わざわざ日本刀を振りかざして突撃する必要性は皆無です。
そのため、常識的に考えてこの「日本刀の切味を喫したる敵の死体六、七十」が戦闘で斬殺されたものでないのは明らかですが、いわゆる「据え物斬り」ならあり得ます。敗残兵掃討で捕らえた捕虜を跪かせて試し斬り(据え物斬り)するなら、日本刀も使えるからです。
この泰山弘道従軍日記に記述された「我が日本刀の切味を喫したる敵の死体六、七十あり」の部分の死体は、戦闘中に殺されたものではなく、敗残兵の掃討で捕縛した敗残兵を「試し斬り(据え物斬り)」によって斬殺したものと考えるのが自然でしょう。
しかしそうであれば、先ほどから繰り返し述べてきたように、敗残兵捕虜はハーグ陸戦法規で人道的な対処を取ることが求められているうえ、処刑するにしても軍事裁判(軍法会議)を省略することはできないわけですから、軍事裁判(軍法会議)に掛けずに即時に斬殺したと思われるこれら敗残兵の殺害は「不法殺害」というほかありません(※この点の詳細も→南京事件における捕虜(敗残兵)の処刑が「虐殺」となる理由)。
したがって、この記述にみられる「我が日本刀の切味を喫したる敵の死体六、七十あり」と描写された死体は、日本軍による「虐殺」の跡ということになります。
(6)昭和12年12月18日「我軍の手により保護せられ」
泰山弘道従軍日記の昭和12年12月18日には、孫文の陵墓だった中山陵を訪れた際の記述があります。
〔中略〕周囲の山腹も巧なる迷彩遮蔽物にて包みありて、中国人が此の陵を兵燹より守らんとせる心尽しの窺ふべきあり。さもあらばあれ、敵の文化を尊重せらるる松井軍団総司令官が、南京突入に際し全軍に布告を発し、中山陵及明考陵を凌辱すべからずと之を保護せられたることや、此処に於て我兵は之に近づかざりしならんも、敵は此処に拠りて我に抵抗したれば、砲弾を見舞うも止むを得ざりしならんか。〔中略〕孫文の眠れる遺骸安置の室は我軍の手により保護せられ、堅く鍵を鎖し入るべからず。
この点、この記述からは、南京陥落時点ですでに方面軍司令官の松井大将から中山陵を保護するよう指令が出ていたことが伺えますし、泰山軍医大佐が見た範囲では戦闘で荒れた形跡はあっても日本軍による略奪は見られませんから、この範囲では日本軍による掠奪(略奪)の事実は伺えません。
しかし、折小野末太郎日記(※詳細は→折小野末太郎日記は南京事件をどう記録したか)や伊佐一男日記(※詳細は→伊佐一男日記は南京事件をどう記録したか)には中山陵における日本軍の掠奪(略奪)の記録が見られますので、泰山軍医大佐が訪れたこの後に、日本軍兵士による放火や掠奪(略奪)の非違行為が行われたと考えるべきでしょう。
ちなみに、中山陵に関しては第16師団参謀長の「申送り(申継書)」にも中山陵で日本兵による「悪戯」が頻発していたことを示す記述がありますので、中山陵における日本兵の放火や掠奪(略奪)は公文書でも裏付けられています。
【南京ニ於ケル申送リ要点(申継書)】
一、中山陵ハ悪戯ヲスルモノ多ク恥辱ニ付見物者ヲ制限シツゝアリ将来ニ必要ナカラン
出典:第16師団参謀長中沢三夫『南京ニ於ケル申送リ要点(申継書)』※偕行社『決定版南京戦史資料集』南京戦史資料集Ⅰ475頁下段
こうした記録を踏まえれば、中山陵でも日本兵による略奪や放火があったことは疑いようがありません。
なお、南京市街では日本兵ほどではないにしても中国兵による放火や掠奪(略奪)もあったことがわかっていますが、この泰山弘道従軍日記には「中国人が此の陵を兵燹より守らんとせる心尽しの窺ふべきあり」と記述されていますので、この中山陵に関しては中国兵による掠奪(略奪)や放火は一切なかったことが伺えます。