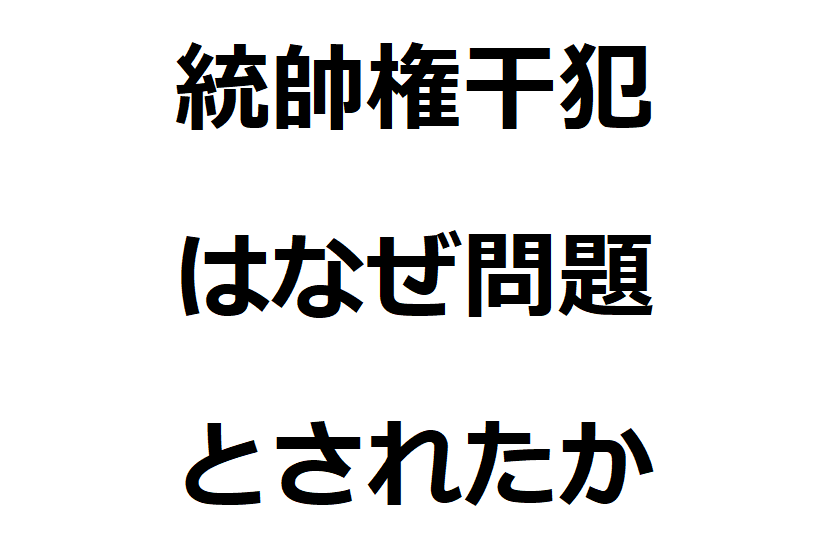こうした中で、加藤軍令部長は政府の一連の行動を「政府が軍令部長の再上奏後裁可を待たずに回訓案を発布した」のは大元帥天皇の統帥権を補翼する軍令部を無視したことになるから統帥権の干犯を受けたことになると受け取り、不満が募っていきます。
4月1日の参内が受け付けられなかったのは単に予定が詰まっていただけであって宮中側に加藤の上奏を阻止する意図はなかったですし(※前述の岡田啓介日記の引用参照)、2日に上奏したときも加藤は政府の意見をなぞるだけで特段の反対意見を述べていなかったわけですからこの加藤の理屈はおかしいのですが、加藤軍令部長はとにかくそう理解した(または青年将校の突き上げがあってそう言わざるをえなかった)わけです。
昨一日以来政府の専横なる処置に憤激せる部内外人心の激昂極度に達し、予に死諫を進める者あり、即時辞職を勧告する者あり。ことに青年将校の態度すこぶる憂慮すべきものありて予の軽挙を許さず。……(※当サイト筆者中略)
※出典:加藤寛治日記 昭和5年4月2日部分より『昭和四年五年 倫敦海軍条約秘録 故海軍大将加藤寛治遺稿』昭和31年9月 |半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅱ」ちくま文庫 83頁より引用
…問題の重点は政府が軍令部長の再上奏後裁可を待たずして回訓を発布せることにありて、統帥権干犯はこの一事に成立す。
いずれにせよ、こうして政府の回訓案は閣議決定され天皇の裁可も得られたわけですが、加藤軍令部長や軍令部の青年将校ら強硬派の中に統帥権干犯の憤怒を残すことになったのです。
政友会の犬養毅・鳩山一郎による統帥権干犯の追及
そうした中、この「統帥権干犯」の問題は海軍内部だけでなく、国会でも取り上げられることになります。追及したのは、政友会の犬養毅と鳩山一郎でした。
4月25日の衆議院の施政方針演説で幣原外相がロンドン海軍軍縮条約について演説すると、本会議場の檀上から政友会の犬養毅や鳩山一郎らが、国防兵力量の決定は統帥事項で内閣と統帥部との共同輔弼事項だから軍令部の同意を得ずに回訓案は閣議決定したのは統帥権の干犯じゃないか、と本会議場の檀上から批判したのです(※頁末半藤書「昭和史の転回点」17頁)。
もっとも、この理屈は成り立ちません。条約を締結するのは政府(海軍省も含みます)であって軍令部ではなく、その責任と権限は明治憲法の下でも政府にあり、天皇の統帥権を補翼する軍令部の意見は参考にすれば足りるのであって、最終的な判断を如何にするかは政府の専権事項と言えるからです。
しかも、前述したように軍令部長の加藤寛治は海軍の「政府が決定した回訓案の範囲で善処するよう努力する」とする方針については岡田啓介(軍事参議官)との話や海軍首脳会議で了承していて、「国防兵力量」を「政府が決定」すること(政府に国防兵力量の決定権限があること)は、軍令部長の加藤寛治も認めていたといえます。
こうした事実からも「統帥権干犯」などはありようはずがなく、軍令部側が干犯などと言える筋合いはないのですが、軍令部と通じた野党は政府の対応を攻め立てていきました。
ただ、建艦競争による財政圧迫を懸念する世論や新聞は概ね政府に好意的で政友会のこの論調に批判的でしたから、ロンドン海軍軍縮条約は政府の回訓案で調印されます。
しかし、海軍の中では政府の回訓案(補助艦の対米比率を7割・6割・5万2千トンとする案)に納得できない青年将校らの憤怒が満ち溢れるようになっていきました。
この点、岡田啓介(軍事参議官)の日記には加藤軍令部長と次のような会話があったことが記録されています。
又海軍部内にも二三変な事をする者はなしとは言い得ざるも、長年先輩の努力により軍紀を保ち来りたる海軍に、此問題の為重大事件起るとは考えずと申たるも、部長は君は何も知らんのだ、それは大変な事になって居ると云えり。予は君や我々が居てそんな事をさしてはいかんではないかと云いたるに、我々では抑えられぬと云う。
※出典:岡田啓介日記 昭和5年5月7日部分より『現代詩資料7 満州事変』昭和39年4月25日 みすず書房|半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅱ」ちくま文庫 71頁より引用
若手将校の不満は、加藤軍令部長ら軍令部幹部が抑えきれないほどにまで沸騰していたのかもしれません。
加藤軍令部長の辞意上奏と草刈少佐の自殺
こうした統帥権干犯の追及が始まり、海軍内部でも青年将校を中心とした強硬派の憤怒が増していく中で、2つの事件が起こります。一つは加藤寛治(軍令部長)の辞意の上奏、もう一つは軍令部参謀草刈栄治少将の自殺です。
5月18日に財部彪(海軍大臣)が帰国すると、加藤は辞意を記した上奏文(奉乞骸骨上奏文)を財部彪(海軍大臣)に提出しました。当時の軍は天皇の統帥の下にあるので辞職するには天皇の許しがなければならず、そのためには海軍大臣から辞意を上奏してもらう必要があるからです。
辞任理由は「統帥大権を奉公するに臨み、参画機宣を失し、兵政の紛糾を致し、国防の基礎ややもすれば動揺を免れざらんとするを見て」としていますから(※頁末「奉乞骸骨上奏文」参照)、ロンドン軍縮条約に関して政府に軍令部の統帥事項(国防兵力の決定)を干犯されて統帥権を補翼できなくなり、このことで軍事と政治に混乱を招いたので責任をとって辞任したいということなのでしょう。
つまり加藤は「政府の統帥権干犯が起きたから軍事と政治に混乱を招いたんだ」と政府を批判しつつ辞職を願い出たわけです。
もっとも、統帥権干犯云々は憲法解釈の意を含みますが軍部に憲法解釈を上奏する権限はありませんし政府回訓案は軍令部長側も了承の上で裁可を受けたわけですからこの加藤の上奏文(骸骨上奏文)は事実とも異なります。またそうした内容は政府の回訓案に裁可を与えた天皇を迷わすことになりますから、財部彪(海軍大臣)はそのまま保留ということにして天皇に取り次がずこの辞表を留め置きました。
そして5月20日には、ロンドン軍縮条約に反対だった軍令部の参謀、草刈栄治少佐がロンドン軍縮条約の調印に抗議して東海道線の車中で自刃(自殺)するという事件まで発生してしまいます。
こうした事件もあったことから、調印されたロンドン軍縮条約に反対する海軍の強硬派青年将校を中心に統帥権干犯の追及はますます過熱していくのです。
軍令部(強硬派)と海軍省(国際協調派・条約派)の対立と統帥権干犯問題の処理
こうした強硬派を刺激する事件が続いたことから軍令部の若手将校を中心に統帥権干犯の追及はますます大きくなっていきました。
海軍省(国際協調派・条約派)と軍令部(強硬派)の対立激化
統帥権干犯の問題は、明治憲法第12条の大権事項たる「兵額と編成の権限」が、海軍大臣(軍政)にあるのかそれとも統帥部長(軍令)にあるのか、つまりその「兵額と編成の権限」が海軍省にあるのか軍令部にあるのか、という命題に集約されますから、「その決定権は軍令部長にもあって海軍大臣との共同補翼事項だから政府が一方的にそれを決めるのは統帥権干犯だ」と考える軍令部(強硬派)と、「その決定に際しては軍令部と海軍大臣の意見が一致することが望ましいけれども、その決定権は海軍大臣も含めた政府にあるのだから軍令部の意見は参考にすれば足りるのだ」と考える海軍省(国際協調派・条約派)の間で意見が真っ二つに割れ、内部対立が激化していったのです。
統帥権干犯問題の処理
ここまで大きな議論になってくると海軍としてもその統一した見解を決定しなければなりません。
そこで財部彪(海軍大臣)と加藤寛治(軍令部長)は昭和5年(1930年)5月29日の軍事参議官会議にそれぞれ海軍省と軍令部双方の統帥権干犯問題に関する見解を提出し、判断を仰いだ結果、最終的には海軍省側の見解の方がよかろうということになってとりあえず海軍省側の意見が通りました。
統帥権干犯問題の海軍側の見解とは、要約すれば以下のようなものになります。
「……海軍大臣が兵力伸縮に関するがごとき海軍軍備に関する事項を決裁する場合には、海軍大臣・軍令部長両者間に意見一致しあるべきものなり」
※出典:半藤一利著「昭和史の転回点」図書出版社 23頁より引用
しかし、この「海軍大臣が…」という文言があることで「兵額と編成の最終決定権は海軍大臣にある」と読めるところに納得いかない加藤寛治(軍令部長)はいったんそれに了承したものの後になってその部分を削除するよう求めだし、海軍重鎮の東郷平八郎や伏見宮からも「海軍大臣が…」の文言は削除したほうがよかろうという意見がでてきます。
そうした経緯もあったことから、最終的には昭和5年6月23日の軍治参事官会議で次のような双方の見解を折衷した文章が海軍の統一した統帥権干犯問題に関する覚書として採決されることになったのです。
「海軍兵力に関する事項は、従来の慣行によりこれを処理すべく、この場合においては海軍大臣、海軍軍令部長間に意見一致しあるべきものとす」
※出典:半藤一利著「昭和史の転回点」図書出版社 34頁より引用
こうして、ロンドン軍縮条約に絡む政府の統帥権干犯問題については一応の解決をみるに至ったのです。
加藤寛治(軍令部長)の辞職問題の処理
一方、加藤寛治(軍令部長)の辞職問題は前述したようにその上奏文(加藤の辞意表明文)の内容に問題があったことから財部彪(海軍大臣)の下に留め置かれていましたので、財部はこれも処理しなければなりません。
前述したように、加藤寛治(軍令部長)は「政府が軍令部の統帥事項を干犯したから職責を担えないので責任をとって辞める」という趣旨の上奏文をもって辞任を求めていますがそれは事実ではないですし、そんな上奏文を出せば天皇を悩ますだけなので取り次ぐことはできないからです。
しかし加藤寛治(軍令部長)の目的は自分が単に辞任して後任に譲るというのではなく、統帥権干犯を陛下に上奏して政府の非を訴えるところにありますから、その上奏文を陛下に上奏しろと譲りません。
また加藤寛治(軍令部長)は、宮内省御用掛の立場を利用して統帥権干犯問題に関する軍令部の批判を昭和天皇にこっそり伝えるなど暗躍が目に余った軍令部次長の末次信正(海軍中将)について財部彪(海軍大臣)が更迭人事を決定したことも不服でしたから、財部と加藤の意見が対立し話の落としどころがつかめない状況がつづきました。
そうした中、昭和5年6月10日になると加藤が自ら宮中を参内して辞任の上奏をしてしまいます。上奏文は加藤が財部に出した上奏文(骸骨上奏文)と同じ政府の統帥権干犯を非難する内容を含む辞意の表明です。
もちろん、軍令部長の辞意の上奏は海軍大臣を経てなされるのが当時のルールですから、天皇はこれをいったん受け取ったもののすぐに財部彪(海軍大臣)を参内させて下げ渡しました。
加藤が辞表を出したのは、財部の帰朝后の事であるが、それは次の様な、経緯がある。当時軍令部次長の末次〔信正〕は、宮内省御用掛として私に軍事学の進講をしてくれてゐたが、進講の時、倫敦会議に対する軍令部の意見を述べた。これは軍縮に対する強硬な反対意見で加藤軍令部長の上奏内容とは異るものであった。そして末次は後で加藤にこの事を話したと見え、加藤は軍令部の意見が図らずも天聴に達し云々の言葉を用いて辞表を直接私の処に持つてきた。末次のこの行為は、宮中、府中を混同する怪しからぬことであると同時に、加藤が海軍大臣の手を経ずに、辞表を出した事も間違ってゐる。私は辞表を財部に下げたら、財部は驚いて、辞表はどうか出さなかった事にして頂き度いと云つた。
※出典:「昭和天皇独白録」文芸春秋社 26~27頁より引用
ただし、こうした加藤寛治(軍令部長)の権限を逸脱した暴挙はそのままにしておけませんから何らかの処分が必要です。
そのため財部彪(海軍大臣)は加藤寛治(軍令部長)を軍治参事官に異動させ、代わりに谷口尚真対象を軍令部長に据える人事を天皇に報告し、それが了承されて加藤寛治軍令部長は辞任ということになりました。
東郷平八郎の海軍省批判と財部彪の辞任要求
こうしてロンドン軍縮条約にからむ統帥権干犯問題と加藤寛治(軍令部長)の辞職問題は内々に処理され落ち着くかに思われましたが、時事新報の6月23日朝刊で海軍における一連の内部抗争の詳細がスクープされてしまいます(※頁末半藤書「昭和史の転回点」34頁)。
政府(海軍省を含む)が軍令部の反対意見を無視して国防を危うくする軍縮条約に調印したという論調で、軍令部側から政府を批判し条約批准に反対する内容でした。
そうなると政府を倒したい野党の政友会や民間右翼なども騒ぎだすので、そうした声の助けもあった軍令部の強硬派は勢いを増します。
条約調印にかかわった財部彪(海軍大臣)や岡田啓介(軍事参議官)、浜口首相に先んじて昭和天皇に反対意見を上奏にしようとした加藤寛治(軍令部長)を諭した鈴木貫太郎(侍従長)の責任追及にまで話は発展し、財部彪(海軍大臣)の辞任を求める声まで出てくるようになりました。
さらに、海軍重鎮の伏見宮は条約に不満はあるもののいったん調印されたからには批准しなければならないと批准に一応賛成しますが、軍令部の強硬派に取り込まれた東郷平八郎からは条約批准の反対と財部外相の辞任を求める意見が出てくる始末です(※頁末半藤書「昭和史の転回点」36~40頁)。
結局、財部を辞任させることで東郷も納得し、昭和5年10月2日にロンドン軍縮条約は批准されますが、同日に財部彪は海相を辞任することになり、海軍内部の海軍省を中心とした「国際協調派・条約派」と軍令部を中心とした「強硬派」の内部対立は火種を抱えたまま残っていくことになりました。
そしてこの対立が対米英開戦への決断へと影響を及ぼし、またこの統帥権干犯の論争が「統帥権の独立」という思想にまで昇華され「統帥権は内政や外交の枠外にある独立したものだから軍事に関することは内政(政治)や外交によって左右されることはない」などと軍部の独断専行を正当化させてその後の二・二六事件や敗戦に至るまでの軍部の横暴につながっていくわけですが、そこまで続けると長くなりすぎるので統帥権干犯についてはこの辺で終わりにすることにいたしましょう。
・半藤一利著「昭和史の転回点」図書出版社刊 6~45頁
・半藤一利著「昭和史1926-1945」平凡社50~51頁
・岡田啓介日記「現代詩資料7 満州事変」昭和39年4月25日 みすず書房|半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅱ」ちくま文庫 64~77頁
・加藤寛治日記「昭和四年五年 倫敦海軍条約秘録 故海軍大将加藤寛治遺稿」昭和31年9月 |半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅱ」ちくま文庫 78~89頁
・加藤寛治 奉骸骨上奏文「昭和四年五年 倫敦海軍条約秘録 故海軍大将加藤寛治遺稿」昭和31年9月 |半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅱ」ちくま文庫 61~63頁
・「昭和天皇独白録」文芸春秋社 26~27頁