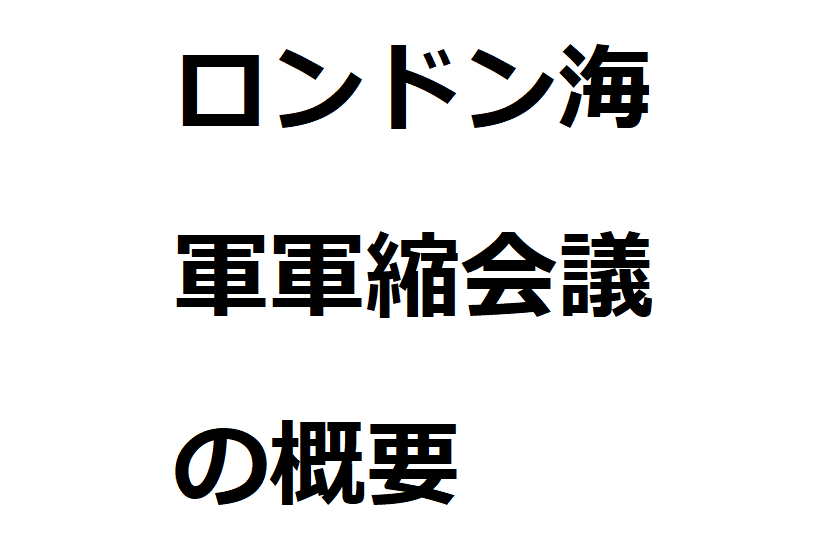ロンドン海軍軍縮会議とは、昭和5年(1930年)1月21日からロンドンで開かれた海軍軍縮会議のことを言います。
会議が開かれた当時、世界恐慌のあおりで世界経済は危機に瀕していました。
昭和4年(1929年)10月にニューヨークのウォール街に端を発した株価大暴落(いわゆるブラック・チューズデイ)の影響が瞬く間に世界に拡散し世界的な大恐慌となって世界経済を破綻の危機に陥れたのです。
欧米列強を中心とした世界各国は経済の再建が急務となりますが、財政を圧迫している大きな要因の一つに莫大な予算を必要とする海軍の建艦競争があります。そこで、国際世論は軍縮を望むようになっていったのです。
もちろんこれは日本も例外ではありません。昭和初頭に起きた金融恐慌は収束していたものの、不景気は続き「緊縮小唄」などの小唄まで流行る状況で、そこにもってきてこの世界恐慌です。
咲いた花でもしぼまにゃならぬ ここが財布の あけた財布の締めどころ 時世時世じゃ手をとって 緊縮しょや 緊縮しょ
※「緊縮小唄」作詞 西条八十 作曲 中山晋平
そうした経緯からアメリカが主導して海軍の軍縮を図るべく開かれたのが、このロンドン海軍軍縮会議だったのです。
8年前のワシントン軍縮会議で生じた海軍省と軍令部の対立
ロンドン海軍軍縮会議の内容を確認する前提として、当時の軍縮の流れを確認した方が良いと思いますので、その8年前に行われたワシントン軍縮会議の内容を簡単に振り返ってみることにいたしましょう。
ワシントン軍縮会議は大正11年(1922年)にアメリカのワシントンで開催されましたが、そこでは戦艦や航空母艦など海軍の主力艦の比率をアメリカとイギリスが5、日本が3として軍拡競争を制限する合意が結ばれました。いわゆる「五・五・三」の比率です。
この比率に関し、日本海軍の軍令部では対米比率が七割以上なければ国防に支障をきたすと考えていたため大反対しましたが、全権大使として出席した海軍大臣の加藤友三郎(大将)は近代戦が総力戦であることを十分に理解していましたので何としても軍縮条約を成立させなければなりませんでした。
第一次世界大戦は図らずも近代戦が戦場で戦う軍隊の優劣ではなく工業力やそれを支える経済力など国家の総力が勝る方が戦争に勝つ国家総力戦であることを証明しましたので、国力の劣る日本が米英と軍拡競争を続ければ国家が破綻して総力戦に堪えられないと考えたからです。
結局、全権大使の加藤友三郎は軍令部の反対を何とか抑えることで「五・五・三」の軍縮条約に調印することができましたが、このワシントン軍縮条約の締結を契機として、日本海軍の内部で軍令部を中心とした強硬派と、海軍省を中心とした国際協調路線(軍縮路線)とが対立する構造が前面に出てくるようになります。
そしてこの対立が、昭和5年のロンドン海軍軍縮会議でもまた問題を生じさせることになるのです。
ロンドン海軍軍縮会議で日本側が提示した「七割・七割・七万八千トン」
こうして戦艦や航空母艦など海軍の主力艦については軍縮条約が結ばれていましたが、巡洋艦や潜水艦など補助艦についてはいまだ手付かずでしたので、それでは補助艦についても軍縮を話し合おうというのがロンドン海軍軍縮会議の目的でした。
この会議にもちろん日本も招待されます。時の首相は張作霖爆殺事件で総辞職した田中義一内閣の後を継いだ立憲民政党の浜口雄幸です。
浜口首相は世界恐慌のあおりを受けて危機に瀕していた国家財政の立て直しが急務でしたから、軍事費の縮小を実現し国民負担の軽減を図ることが不可欠と考えていました。
国防の問題はありますが、各国が一律に軍備縮小を行うのであれば軍事バランスは損なわれないので、浜口首相は何としてもロンドン海軍軍縮会議を成功させようと考えていたのです。
浜口首相は全権委員として元首相の若槻礼次郎、イギリス大使の松平恒雄、海軍大臣の財部彪(大将)の3人を選任しロンドン海軍軍縮会議に挑ませました。山本五十六(少将)や豊田貞次郎(大佐)などもこれに随行しています。
この点、ロンドン海軍軍縮会議に挑むにあたって、あらかじめ日本側が決めていた三大原則があります。
- 総体の巡洋艦の比率について対米比率7割とすること
- 重巡洋艦の対米比率も7割を維持すること
- 潜水艦は現有トン数の7万8千トンを維持すること
の三つの原則です。
なぜ7割かというと、米英は大西洋にも艦隊を残しておかなければなりませんので、仮に米英が7割を太平洋に派遣してきたとしても「10対7」の比率であれば「14体7」の比率となり、南西諸島の空港や航空戦力などの”地の利”を活用すれば「14対7+α」の戦力比となるので、こちらから攻め込むことはできなくとも攻め込まれることはないと軍令部が考えたからでした。
海軍の作戦を立案し執行するのは海軍の軍令部でしたから、この「七割・七割・七万八千トン」を絶対ラインとして海軍省に提示し、これを浜口首相が受け入れて閣議決定しこの三原則で条約を取り纏めるべく全権委員を送り出したわけです。
ロンドン海軍軍縮会議におけるアメリカの譲歩
これに対してアメリカは「10対6」の比率を主張します。大正11年のワシントン軍縮会議では主力艦について「10対6」で合意したのだから巡洋艦も六割でいいだろう、という理屈です。
この点、若槻礼次郎は「アメリカとしては、十対六ならば、アメリカが日本を攻めて、叩きつけることが出来る、その力を持つ必要があると考えていたんだろう」と自伝の中で述べていますから(※頁末参考文献参照)実際そうだったのでしょう。
一方、日本側、特に海軍の軍令部は用兵上の問題で七割を下回る比率では守れないと考えていましたし、ワシントン軍縮条約では日本側が譲歩して「10対6」で纏めた経緯があり国民の理解が得られないと述べて「10対7」の比率は譲れないと当初の主張に固執します。
話は平行線で行き詰りますが、世界恐慌で軍事費を抑えたいのは相手も同じですので次第にアメリカ側から妥協案が提示されてきます。
アメリカ側との交渉の経過は全権委員の若槻礼次郎が自伝「古風庵回顧録」の中で詳しく語っていますので(※頁末参考文献参照)、以下この回顧録を参考に確認していきましょう。
条約の期限・重巡洋艦の比率
若槻の回顧録によれば、交渉が行き詰っていたところ、アメリカ側から双方各一人の委員を出してフリートークで打開の糸口を探してはどうだろう、という提案があり、日本側から松平恒雄駐英大使を、アメリカ側から共和党のリード下院議員を出して自由な話し合いをさせることになりました。
そのフリートークの場で、アメリカはまず条約の期限を1935年までの5年間に限定しようと提案をしてきています。5年程度の短期であれば、少々の不利があってもお互いに妥協点を見いだせると考えたからです。
また、重巡洋艦の比率について1935年までの5年間は「アメリカ15隻:日本10隻(これで10対7)」とし、33年からアメリカだけが毎年1隻ずつ建造できることにして期限の2年後に完成させるようにする案を提示してきました。
こうすれば、期限内は日本側の「10対7」が維持されますし、期限後にはアメリカは18隻を持つことが出来るようになるので「10対6」となるものの、期限満了後に日本側でも建造に着手すれば日本側にそれほど不利にはなりません。
こうして重巡洋艦の比率と期限については、松平とリードの間で一応の合意を見つけることができたのです。
総体の巡洋艦(補助艦)の比率
次に、今度はアメリカ側全権主席のスチムソンから若槻に直接個別の会談が申込まれ、アメリカから巡洋艦の総トン数の比率を「10対6.975」とする妥協案が提示されます。
日本側の主張は対米比率7割でしたから若槻礼次郎は通訳に「まだ二厘五毛足りないと言え」と伝えますが、その差はわずか「0.25」でほとんど日本側の主張した7割と変わりません。アメリカの当初の主張は「10対6」でしたから、これは相当な譲歩だったでしょう。
そのため通訳の外交官は、アメリカ側も帰国して議会に説明しなければならず、6.975なら日本の言いなりに全部譲ったんじゃないという理屈が成り立つので0.25だけ削った妥協案を提示してるんだろうからそこまで言わない方がいいとやんわりと諭します。
それで若槻もようやくこれでよかろうとこれに同意しました。
潜水艦の比率
潜水艦については、日米の会議の中でアメリカ側から日米の総トン数をそれぞれ5万2千トンの同数とする提案がなされます。
5万ン2千トンという数字は、日本が現有の潜水艦7万2千トンから新造艦を作らず廃艦すべきは廃艦にした場合に5年後に何トンになるか尋ねられた際、日本側が5万2千トンと回答した経緯があったからでした。
この数値であればアメリカ側は5万2千トン以上の潜水艦は作れないので日本に不利はありませんし、アメリカの当初主張した「10対6」で計算すれば12万トンになるところをその半分以下にまで削ったわけですからアメリカ側としては相当な譲歩です。
こうして若槻は、潜水艦についても合意点を見出すことが出来たのです。
軍令部の反対(軍令部と海軍省における対立の再燃)
こうして若槻は松平・リードのフリー会談なども利用してアメリカ側と妥協点を見つけることができました。もっとも、調印するには政府の許可や天皇の裁可がなければなりませんので東京にいったん打電する必要があります。
- 総体の巡洋艦の比率の対米比率を「10対6.975」とする
- 重巡洋艦の対米比率は「10対6」とする(※但し1933年までは10対7)
- 潜水艦は日米双方5万2千トンとする
ところがこの時、同行してきた海軍随員の多数から反対意見が出されます。海軍としては「10対7」が用兵上の限界だと判断していて、それを下回る条約に調印すべきではないと考えていたからです。
随員としてきた海軍の将校から政府に反対意見を出すと言われますが、若槻は首席全権を承諾する際、国民の負担を軽減するために自分の命と名誉をかけて会議に挑むと決意していましたので、アメリカ側と纏めることのできた妥協案を政府に打電してその許可を求めました。
当然、東京でも激論が交わされます。もちろん緊縮路線で国家財政の健全化を図ろうとする浜口首相は若槻の妥協案で条約を結ぼうと考えますが、「10対7」に固執する軍令部と国際協調路線に立って国防を図ろうと考える海軍省の間で意見が割れたからです。
こうしてワシントン軍縮会議の時に生じた海軍内部における軍令部と海軍省の対立が再燃することになりました。
この対立が、やがてその後の日本の行く末に大きな影響を及ぼすことになる、いわゆる「統帥権干犯問題」に発展するわけですが、そこまで綴ると話が長くなりすぎるので、それはまた別のページ(※統帥権干犯問題とは(ロンドン軍縮条約の海軍省と軍令部の対立))で解説することにしましょう。
ロンドン海軍軍縮条約(1930年ロンドン条約)の調印
もっとも、こうした海軍内部での対立と反対意見がありながらも、最終的には軍令部が折れて海軍側の意見が纏まり、若槻の妥協案を若干修正した回訓案が閣議決定され、天皇の裁可を得てロンドンに打電されました。
こうして、ロンドン海軍軍縮会議は合意が形成されることになり、昭和5年(1930年)4月22日にロンドン海軍軍縮条約(1930年ロンドン条約)が調印されることになったのです。
・若槻礼次郎「ロンドン会議の回想」『古風庵回顧録』若槻礼次郎自伝ー明治、大正、昭和政界秘史 昭和25年3月25日発行 読売新聞社|半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅱ」ちくま文庫 41~53頁
・半藤一利著「B面昭和史 1926~1945」平凡社ライブラリー 69頁
・半藤一利著「昭和史の転回点」図書出版社刊 6~13頁