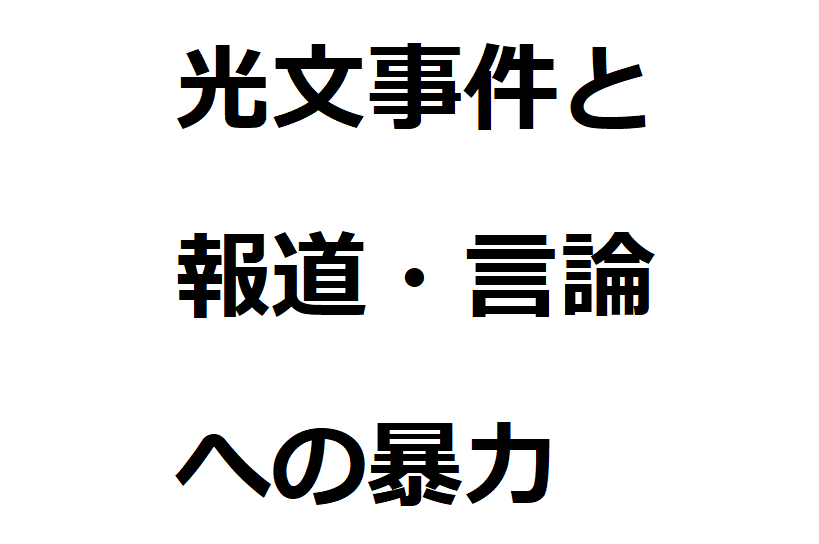光文事件とは、大正から昭和に元号が変わる際に、東京日日新聞(現在の毎日新聞)が新元号を「光文」と誤報してしまった事件のことを言います。
神奈川県葉山の御用邸で病気療養中だった大正天皇は大正15年(1926年)の12月になると病状が悪化し12月25日の午前1時25分に崩御されました。
宮城(※皇居のこと。戦前は「宮城」と言っていました)では皇位を承継した昭和天皇に三種の神器を移す剣璽の渡御の儀式(剣璽渡御の儀)が行われましたが、その後すぐに御用邸内で枢密院会議が開かれます。喫緊に求められるのが「元号」の選定だからです。
といってもその御用邸での枢密院会議で元号の選定が一から行われたわけではなく、大正天皇崩御に備えて早い段階から元号の選定作業は行われていました。
宮内省(現在の宮内庁)では一木喜徳郎宮内大臣を中心に元号草案の作成が始められていて「昭和」や「上治」など43の元号候補がすでに挙げられていたのです。
しかし、この43個の元号案の中には「光文」は挙げられていませんでした。ではなぜ、東京日日新聞(今の毎日新聞)が新元号を「光文」と誤報してしまったのでしょうか。
枢密顧問官のルートから情報が「光文」の誤報につながった(と思われる)
光文事件の経緯については半藤一利氏の「B面昭和史(平凡社ライブラリー)」や「昭和史探索 Ⅰ(ちくま文庫)」で詳しく解説されていますのでそちらを読んでいただくのが早いと思いますが、同書によれば東京日日新聞が誤報に至ってしまった理由として枢密顧問官のルートから独自の情報を得ていた可能性が挙げられています。
前述したように新元号の選定は枢密院会議で議論されていましたが、それとは別に枢密顧問官他が集まって元号案を考えていて、その密儀のなかに「光文」があり、その枢密顧問官のルートから東京日日新聞が情報を得ていた可能性があることが『毎日新聞七十年史』からわかっているそうです。
新元号が何に決定されるかは当時も今と同様に国民最大の関心ごとでしたから新聞各社はこぞってスクープを狙っていました。もちろん東京日日新聞もその例外ではなく様々なルートから情報を収集していたわけです。
このあたりの経緯は当時大阪毎日新聞社(※明治44年に東京日日新聞を合併しています)に勤務していた阿部真之助氏(のちにNHK会長)が後年になって文芸春秋に寄せた回顧録『「昭和」という名の年号』に詳しいですが、同回顧録によれば葉山に詰めていた政治部の記者から「年号は光文、天文の二つのうちから決められるだろう」という情報が入ったものの「天文」は戦国時代に一度使われた年号だったため同一年号が重複して定められることがありうるかという点が議論になったそうです。
そうこうするうちに今度は先ほどの枢密顧問官のルートの数人の記者から「年号は光文に決定すること確実だ」という情報が入ってきます。
そのため、これはスクープだということで東京日日新聞と大阪毎日新聞が25日の午前3時過ぎ、元号を「光文」とする号外を出してしまったのです。
ところが25日の正午になると朝日新聞や時事新報が「昭和元年ト為ス」との勅語が出た旨の号外を出し、新元号が「昭和」であったことが伝わります。
これが「光文」事件の経緯です。
「光文」の号外を見て枢密院が急遽「昭和」に差し替えたという事実はないらしい
この点、「光文」の号外が出されたことから「報道どおりに光文に摺れば枢密院の沽券にかかわる」ということで当初きまっていた「光文」から急遽「昭和」に差し替えたという説もあるようですが、これは事実ではないようです。
前掲の半藤氏「B面昭和史」では「とどのつまりは伝説にすぎず」と書かれていますし(同書13頁)、前掲した阿部真之助氏の回顧録でも以下に引用するように枢密院会議では当初から昭和にきまっていたと述べられています。
世間では毎日の予報をみて、枢密院が俄かに「光文」を「昭和」に摺り替えたと、伝説的に伝えているが、私の知る限りでは、枢密院が故意に変更したという事実はないようだ。始めから原案が昭和で、昭和にきまったもののようだ。
※出典:阿部真之助著『「昭和」という名の年号』「文芸春秋」臨時増刊 昭和メモ 昭和29年7月5日発行 文芸春秋社刊(※半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅰ」ちくま文庫 39頁を基に作成)
また、若槻礼次郎(大正15年から昭和2年まで首相)の回顧録でも、「昭和」は書経の堯典にある「万邦協和、百姓昭明」から取ったものだが堯が行ったのは共和政治のようなものであって天皇制の日本では好ましくないから易経からとった「上治」にすべきだという意見があったものの枢密院会議では異議なく「昭和」に決定したと記されています。
倉富のいうには、「万邦協和」うんぬんの言葉は、書経中の堯典にある。堯は禅譲の天子で、位を子孫にお譲りにならないで、舜に譲り、舜は禹に譲って、今日でいう共和政治のようなものだ。だから「昭和」はいかん。それよりも「上治」の方がいいというのであった。これは後の話だが、西園寺公がこのことを聞かれて、日本の元号には、今まで書経から出た者がたくさんあるじゃないか。それを今になって彼れ是れいうことはない。書経で宜しいと云って笑われた。とにかくこの時の枢密院会議は、倉富の説が出ただけで、誰も異議なく「昭和」に決定した。
※出典:若槻礼次郎著『「昭和」の年号』 「古風庵回顧録」読売新聞社刊(※半藤一利編著「昭和史探索 Ⅰ」ちくま文庫32~33頁)
一部のテレビドラマなどでは「光文→昭和差し替え説」に基づく脚本がとられているようですが、枢密院では当初から「昭和」に決まっていて東京日日新聞の「光文」はただの勇み足で明らかに単なる誤報だったというのが史実のようです。この手のドラマはフィクションとして楽しんだ方が良いのかもしれません。
光文事件は報道に対する「愛国者」の暴力が横行する昭和の時代の幕開けを象徴する事件だった
このように、光文事件は明らかな東京日日新聞による「誤報」だったわけですが、この事件は単なる「誤報」というだけのものではありません。
報道の自由に対する暴力が横行する昭和の時代の幕開けを象徴する事件でもあったからです。
太平洋戦争の最中は軍部が新聞や雑誌などのメディアに介入し検閲を徹底するなどしただけではなく、民間右翼が幅を利かせて報道や政治に介入することが多々ありましたが、そうした暴力による報道の自由(表現の自由)への介入はそれ以前までは顕著ではありませんでした。
では、いつごろから暴力が幅を利かせて報道の自由を抑えるようになったかというと、前に挙げた阿部真之助氏の回顧録は以下に引用するように大正後期から徐々に「愛国者」が幅を利かせるようになったと述べています。
明治の末年から、大正の初期にかけては、暴力団も微力で、甚しく新聞の煩いとなるほどのことはなかった、それが俄かに暴威を振うようになったのは、床次竹二郎が内相時代、全国の博徒を糾合し、国粋会を創めて以後のことであった。世の中の日陰者となっていた彼等が、国粋者として、愛国者として表面に浮かびだし、大手を振って横行するようになって以来の減少だった。床次という政治家は、いまの流行語で言うと、毛ナミのいい人柄で、いまもってその徳をたたえる人があるようだが、暴力を地下から引き出した一点において、私はどうしても彼を買うつもりにはならないのである。
※出典:阿部真之助著『「昭和」という名の年号』「文芸春秋」臨時増刊 昭和メモ 昭和29年7月5日発行 文芸春秋社刊(※半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅰ」ちくま文庫 37頁を基に作成)
床次竹二郎は1918年(大正7年)9月の原(敬)内閣で内務大臣に就任し1921年(大正10年)11月4日に原敬が暗殺された後に内閣を引き継いだ高橋是清が1922年(大正11年)6月に退陣するまで留任していますから、この頃から徐々に民間右翼が幅を利かせるようになって暴力で報道を抑え始める風潮が広がり始めたのがわかります。
特に、皇室関係の報道には慎重を要し、少しでも誤植や誤報があると、そうした人たちが新聞社等に押しかけてきて脅迫し金銭を要求するようなことが横行していたようです。
一体皇室記事の報道ほど新聞および記者にとり、ニガ手はなかった。一点一画でも誤植や誤報があると、どこからか暴力団がやってきて、新聞社を脅迫した。(※当サイト筆者中略)オドカシと高をくくっていても、ピストルや短刀を目の前に突きつけられての交渉である。いい心持がするはずがなかった。(※当サイト筆者中略)あるいは暴力恐喝者を、警察につき出せば片附くと考える人があるかも知れない。しかし愛国兼暴力業者に対しては、警察はまったく無力だった。新聞は無警察の状態において、自からを守らなければならなかったのである。
※出典:阿部真之助著『「昭和」という名の年号』「文芸春秋」臨時増刊 昭和メモ 昭和29年7月5日発行 文芸春秋社刊(※半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅰ」ちくま文庫 35~36頁を基に作成)
こうした民間右翼の暴力は当然、光文事件の際も影響を与えたようです。今の世の中であれば仮に誤報や誤植があったとしても、せいぜい謝罪広告や謝罪記事を出すぐらいで悪くしても責任者が記者会見で頭を下げるぐらいで済むだろうと思いますが、光文事件のあった昭和元年ごろではそうはいきません。
大阪毎日新聞の本山社長が処分の甘さに激怒したこともあり、副主幹などの減俸だけでなく、編集局の責任者が東京日日新聞から大阪毎日新聞に(またその逆に)異動になるなど果断な処分が下されました。ちなみに「光文」の情報を取ってきた担当記者は退社してしまいます。
こうした加重な処分は新聞の信用を損なったことや皇室への申し訳なさなどもあったと思われますが、前掲の阿部真之助氏の回顧録は次のように脅迫に堪えかねた面もあったろうと述べています。
本山社長の激怒したのは、この誤報により新聞の信用を傷けたその責任を問うということもあろう、天子様に申し訳ないという心持もあったであろう。しかし頻々とやってくる脅迫に堪えかねたということもあるに違いなかった。
※出典:阿部真之助著『「昭和」という名の年号』「文芸春秋」臨時増刊 昭和メモ 昭和29年7月5日発行 文芸春秋社刊(※半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅰ」ちくま文庫 41頁を基に作成)
つまり、こうした「愛国者」が、マスコミ・メディアあるいは言論人などの言論・報道・表現の自由を暴力をもって押さえつける風潮が勢いを増しつつあった当時の世相を象徴しているのがこの「光文事件」であったということが言えます。
・半藤一利著「B面昭和史 1926-1945」平凡社ライブラリー
・阿部真之助著『「昭和」という名の年号』「文芸春秋」臨時増刊 昭和メモ 昭和29年7月5日発行 文芸春秋社刊(※半藤一利編著「昭和史探索1926-45 Ⅰ」ちくま文庫)